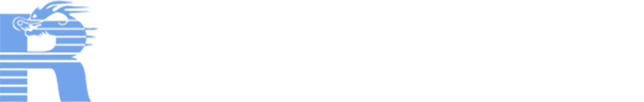胸やけする方へ、逆流性食道炎!
こんにちは!神田第一接骨院です!
今回は逆流性食道炎についてです。
逆流性食道炎とは
逆流性食道炎とは、胃の中で胃液と混ざり合った食べ物や胃液そのものが食道に上がってきて逆流する病気です。
食道には酸から守る粘液が少ないため、強い酸(PH1~1.5)によって粘膜がダメージを受けます。
胃液は強い酸性のため、食道に上がって逆流すると、食道の粘膜を刺激して食道の粘膜がただれたり、潰瘍ができたりします。
原因
食道と胃のつなぎ目である噴門部には、下部食道括約筋という筋肉があって、食べ物を飲み込む時以外はこの筋肉が食道を閉めて胃液を逆流させないようにする働きがあります。
逆流性食道炎は、下部食道括約筋の機能が落ちこの仕組みがうまく働かなくなることで、胃液が逆流を起こし食道に炎症が広がり起こります。
さらに、食道の蠕動運動が低下すると、胃の内容物が逆流したときに、胃にもどすことができず、食道に炎症を起こす原因となります。
逆流性食道炎の主な原因として、脂肪分やタンパク質の多い食事、食べ過ぎ、加齢、肥満、姿勢の悪さなどがあり、薬の副作用として現れる場合もあるので気を付けなければなりません。
症状
事後の2~3時間までに胃酸の逆流が起こりやすく、以下のような症状が現れます。
・胸焼け
・みぞおちの上が焼ける・滲みるような感じがする
・酸っぱい感じが込み上げる
・腹部膨満感
・胃もたれ
・胸がつまるような痛み
・ゲップが頻繁に出る
・乾いた咳が続く
・喉の違和感(喉がつまった感じ・イガイガする)
・声が枯れる
治療
逆流性食道炎に対する鍼灸、手技を行う治療は、下部食道括約筋の機能向上と消化管全体(食道から腸まで)の動きを高めることを主な目的としています。
1. 後頭下筋群を刺激して迷走神経の働きを高める
後頭部のツボを刺激することで、胃や食道を支配している迷走神経の働きを高め、下部食道括約筋の締まりが良くなり、消化管全体の動きも良くなります。
2. 手や足のツボで食道と胃腸を整える
前腕の手のひら側や足の指の付け根には、代表的な消化器のツボがあります。
感覚が鋭敏な体の末端部を刺激することでも、消化管全体の働きを良くすることが出来ます。
内閣、内庭
3. 表情筋や頭皮の刺激で副交感神経の働きを高める
交感神経が興奮してしまうと、胃腸の働きが悪くなってしまいます。
顔や頭皮を刺激すると、交感神経を鎮静化させ、副交感神経の働きを高めることが出来ます。
副交感神経を高めることで、消化管全体の働きを高めます。
〇場所
神田駅西口より徒歩5分
大手町駅より徒歩7分
小川町駅より徒歩15分
院名:神田第一接骨院
住所:東京都千代田区内神田2-4-13 石垣ビル1階
TEL:03-3256-9400
受付時間:平日 10:00~20:30まで
土曜 10:00~19:00まで